メリットとデメリット:タブレット学習 vs 紙の学習
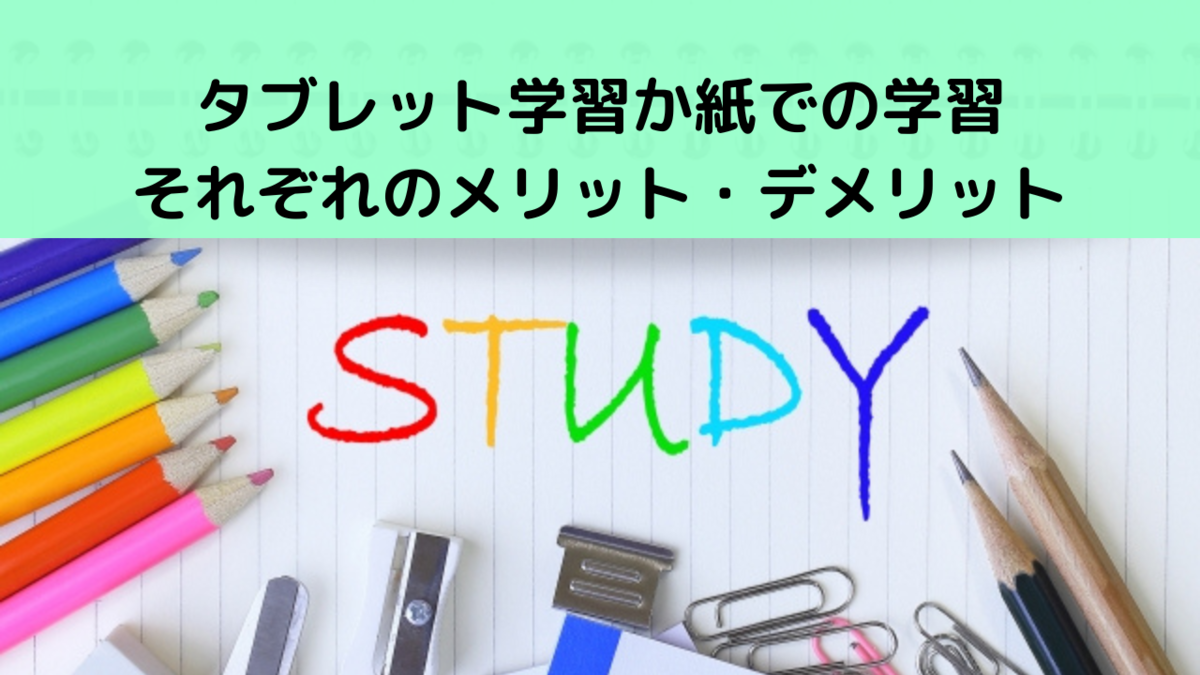
こんにちは。
学校でのタブレット学習が普及するなかで、自宅での学習に関してタブレット学習と紙での学習どちらがいいか悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、タブレット学習と紙での学習、それぞれのメリット・デメリットとおすすめの活用法を紹介したいと思います。
タブレット学習のメリット

特に、算数の図形問題や漢字の書き順、英語の発音などは動画や音声があると理解度は高まるでしょう。
また、採点の手間がはぶけ保護者がつきっきりにならなくてもよい点は、共働き家庭にはメリットといえるでしょう。
私の周りでは、「タブレット1つで国語・算数だけでなく、たくさんのコンテンツができる点はコスパ良い。」との声や、「ゲーム感覚で自分から進んで学習してくれるのは助かる。」との声がありました。
タブレット学習のデメリット
- 紙学習より割高である
- タブレットによってはゲーム性の高いコンテンツがあり、遊びに熱中してしまう可能性がある
- 目が悪くなる可能性がある
- 紙に書くことが少なくなるため、低学年の場合は字が安定しない
- ひらがな・カタカナ・漢字の採点がやや甘く、なぞり書き線から多少ずれていても丸になる
タブレットを使用するときは、時間を決め明るい場所で使用する。
定期的に休憩をいれるなど、視力低下をさけるための配慮をするとよいでしょう。
私の周りでは「タブレット学習をはじめたもののゲーム系のものばかりやってしまい、あまり活用できなかった。」という声や、「夕ご飯を作っている間に自分でやってくれて、自動で採点もしてくれる点は助かる。ただ本人にまかせきりにしていると、きちんとやっていない時もあるから親の確認は必要だと思う。」という声もありました。
紙学習でのメリット

- 筆圧の確認や文字をきちんと書く練習になる(小学校低学年の場合)
- 親が採点することで、できているところ・苦手なところを把握することができる
- 通信教材だけでなく書店でも豊富な種類の教材を購入できる
- 紙での通信教材は、授業の進度に合わせた学習ができるため授業の予習や復習として活用できる
- 通信教材によっては、学校の教科書の出版会社を登録することで、学校と同じ内容の学習ができる(タブレットでも可能なものあり)
- コピーをすれば、間違えた問題は何度も学習することができる
- 文字や図を実際に自分で書くため記憶が残りやすい
- 働く家庭の場合、夏休みなどの長期休暇中、学童クラブに持参することができる
実際、私の子供の所属する学童クラブでは、タブレットは持参禁止です。
休校日の学童クラブでは、朝学習の時間があります。
朝学習とはいっても、マンガを読む子やドリルをする子など過ごし方は様々です。
我が家では、家でコピーした学習教材を1日分ずつホッチキスでまとめておき、毎日持っていかせました。
紙学習でのデメリット
- 低学年の場合、親が採点する必要があり負担が多くなる
- 楽しむ要素が少ないため、子供が自発的に学習しづらい
- 教科ごとに教科書や教材が分かれていると、荷物がかさばる・管理するのに時間を要する
- 書店で選ぶ場合は、どれを選んでいいか悩んでしまう
- 教材がたまり場所をとる
紙学習をする際は、白黒や単色の教材よりもカラーやイラストがあるもののほうが子供の興味をひきやすいでしょう。
年齢別によるおすすめ
低学年の場合、文字の練習やテストの練習にもなるため紙教材がおすすめ。
特に小学校1年生は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字をきちんと書けるようにしておく必要があります。
しかし、学習内容を確認する時間がとれない場合に、子供が教材をやったものの親が確認しないまま放置となってしまう可能性もあります。
その場合はタブレット学習のほうが、親の負担も少なく子供も勉強をスムーズに進めていけるでしょう。
高学年の場合、自分で学習内容の把握ができるため親のサポートは少なくなるかと思います。
その場合、解答にかける時間を省いたり、自動で苦手分野を解析してくれたりとタブレット学習によって効率的な学習をすることができるでしょう。
おすすめ活用法
一番のおすすめは紙学習とタブレット学習の併用でしょう。
紙だけでは理解しにくいことも、動画をみることで理解が深まることも多いです。
しかし、両方となると経済的負担もでてきます。
そこで我が家での活用方法を紹介したいと思います。
我が家では、長男が小学1年生ということもあり、現在は紙の通信教材を利用しています。
ただし、通信教材の中にパソコン上で行えるコンテンツがいくつかあります。
プログラミング・英語・漢字対策・算数計算・オンライン授業などタブレット学習と同様にデジタル学習も可能となっている教材で学習しています。
毎日の学習は紙教材、週末や時間があるときにパソコンを開いてデジタル学習という使い方です。
紙での通信教材を選んだ理由はいくつかあります。
- 筆圧をあげる
- ひらがな・カタカナをきちんと書けるようする
- 教科書を選択することで学校と同じ内容が学習でき、予習・復習につかえる
- コピーをして間違った問題は日にちを少しあけながら正解するまで何度もやる
- 私自身が子供の得意・不得意を把握したい
- よく間違う問題はファイルに管理して定期的にとかせたい
コピーをするのに少し時間がかかる点はデメリットですが、コピーすれば何度も使用できる点はメリットです。
昨年まで我が家にプリンターはありませんでした。
しかし、プリンターを購入してからというもの、教材だけではありませんが1か月100枚以上印刷しています。
最近のプリンターはコピーができたり、スマホとWiFi接続できる機能があったり、パソコンを開かなくても様々な場面で活用できます。
自宅のプリンターはA4サイズが一般的かと思います。
ここでとても役にたつのが、スマホのスキャンアプリです。
教材によってはA4見開きで問題を解く場合に、そのままA4でコピーすると2枚に分かれてしまいます。
そこでスキャンアプリを使用して、見開き状態で写真をとることで1枚にまとめることができます。
スキャンアプリで一通り写真をとって保存しておけば、あとはスマホから画像を選択して印刷ボタンを押すだけでOKです。
こうすることで、長時間プリンタのそばで作業することなく、その間に家事をすることもできます。
まとめ
タブレット学習、紙での学習それぞれにメリット・デメリットがあります。
また、家庭によって家族構成や働く状況、学習にかけられる時間も様々です。
それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、家庭にあう勉強方法をとりいれることが一番効果的な学習になるのではないでしょうか。
ぜひ参考にしていただけると幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
息子が発達障害と診断される②~ADHDの治療内容と実際の効果とは~
前回、発達クリニック初診・検査の内容と診断結果(ADHD+ASD併発)について書きました。
(ADHD:注意欠陥・多動性障害、ASD:自閉症スペクトラム症)
今回の記事では、【ADHDの治療方法と実際に私が選択した治療法、その後症状に変化は見られたのか】について息子の体験とともに紹介していきたいと思います。
ADHDの治療に使用される薬について、「実際の効果はどうなのか?」、「副作用はあるのか?」など気になる方はぜひ参考にしてみてください。
ADHDの治療法
ADHDの主な治療法は、自分の特徴を理解し、状況に応じた適切な行動をとれるようになるための「心理社会的治療」から開始し、必要に応じて「薬による治療」を組み合わせます。
薬による治療とは、脳内の神経伝達物質(ドパミン・ノルアドレナリン)の伝達を改善するなどして、ADHDの症状を緩和します。
最終的にはお薬の力を借りなくても、自分で行動をコントロールできるようになることが治療の目標です。
心理社会的治療とは
ADHDがあっても、周囲との人間関係や日常生活がうまくいくよう環境を整える治療法です。
主には以下の3つになります。
| 環境調整 | 患者さん本人の周囲の人が症状を理解し、患者さんの生活しやすい環境を整える 特性との上手なつき合い方を考えていく |
| ペアレント・トレーニング | 親に対し、患者さんへの対応方法をトレーニングする (完璧を求めない、できることはほめて伸ばしていく) |
| ソーシャルスキル・トレーニング | 患者さんに対し、状況に応じた行動がとれるよう、社会のルールやマナーを教える |
幼少期に行う心理社会療法としては主にペアレント・トレーニングがあります。
ペアレント・トレーニングは親が子どもの行動パターンを理解し、ほめかた、環境調整、問題行動に対する対応を学ぶ方法です。
私が実施していたことは、望ましい行動をとった時に褒めてごほうびをあげる方法です。(トークンエコノミー法)
我が家ではシールを台紙に貼っていき、20個ほど集めると欲しいものがもらえるルール。
例えば、遊び終わったあとに自主的に片付けができたらシール1枚渡していました。
環境調整としては、家の学習机のまわりに勉強と関係ないものは置かない。
学校では、気が散らないように1列目か2列目にしてもらい、廊下側や窓際は避けてもらいました。
学校で生活する時間は長いので、先生に協力してもらいながら学習環境の調整をしたほうが、子どもと先生両方のメリットにつながります。
お薬による治療とは
基本的に薬による治療法は、学童期以降が適応になります。(6歳未満には処方できない)
ADHDの主な治療薬は、コンサータ、ストラテラ、インチュニブ、ビバンセという4種類があります。
それぞれ、集中力を高める・衝動を抑えるなどの効果がありますが、薬が効き始まるまでの期間の差や副作用症状の違いもあるので主治医と相談したうえで選択しましょう。
息子は現在、環境調整やペアレントトレーニングを実施しているが、集中が続かない・忘れ物が多いなどの不注意行動がみられるため、薬による治療が適用と判断されました。
最初に提案されたものは、コンサータ錠もしくはインチュニブです。
コンサータ錠は、1日1回朝服用。
即効性があり、飲んだ当日~数日で効果を感じられる。
処方できる医師が限られている
また、土日や夏休みなど学校がない日は休薬することも可能と言われました。
自分の都合によって休薬日を設けることができるというメリットがある。
(コンサータ錠の休薬・中断は、主治医の指示に従うようにしましょう)
インチュニブは1日1回服用。
即効性はないが持続的に服用することで効果があらわれてくる。(約1~2週間程度)
勝手にやめることはできず、毎日飲み忘れないよう注意しなければならない。

私が選択した薬とは
薬はコンサータ錠を飲み始めました。
理由としては、即効性があるため、どれくらい薬の効果があるか確認したい点、自己都合によって休薬することができる点で選びました。
少しずつお薬の成分が出てくる構造のため、朝服用しても効果は日中約12時間続きます。
コンサータ錠のよくみられる副作用について
・食欲低下・体重減少
服用した方の40%程度に食欲の低下が見られるそうです。
数週間で落ち着いてくるそうですが、特に昼食をあまり食べられなくなる場合があるので、学校の先生に給食の摂取量を確認してもらうと安心です。
夕食もあまり食べられないような場合には、朝の服用時間を早めることで改善することがあります。
息子の場合は、飲み始めから2週間は学校の給食摂取量を観察してもらいました。
毎日報告してもらうのは、大変なので金曜日にまとめて1週間分の状況を教えてもらうようにしました。
・寝つきが悪い
約20%程度の方で寝付きが悪くなることがあるそうで、なるべく早い時間に服用することで改善する場合もあります。
実際に薬を飲み始めての効果と副作用とは
6回目の診察日は息子と一緒に来院
普段の様子の変化と副作用について話し合いました。
薬を飲み始めてからというもの、毎日のように水筒の忘れ物をしていた息子がまったくと言っていいほど忘れ物をしなくなりました。
また、集中力が持続するようになり勉強に費やす時間が大幅に短縮されました。
今までは、学校での様子を聞いても「わからない。別になにもしてない」という返事ばかりだったが、自分から「今日学校でね、おにごっこしたんだよ。」など具体的な出来事を話してくれるようになりました。
お薬を始めて数日で明らかに変化がわかりました。
1か月経過し感じたことは、毎日息子に対して注意したり怒る頻度が減少したということ。
勉強中に中断することが減り、集中力が持続していると実感しました。
ただし、メリットだけでなくデメリットもみられました。
副作用として多い食欲不振。
息子もかなり食欲が減り、本来の半分くらいしか食べなくなりました。
体重も減ってしまい、「このままではまずい!」と思い、食欲がなくてもできるだけたべるように促しました。
少しずつ量が戻り、1か月後には以前と同じ量が食べられるようになりました。
しかし、1か月を過ぎた後も食欲がわかないようで促さないと全量は食べません。
朝食は食べられるので、以前より少し早く起きるようにして朝ごはんを残さず食べられるよう工夫しました。
またその他の副作用として、夜の寝つきが悪いということです。
電気を消し暗闇の中、爪をいじったり寝返りを何度もしたり。
寝付くまでに、30分〜1時間くらいかかります。
できるだけ寝る前のテレビは避け、少しでも眠くなるようにと寝る前に本を読む習慣を心がけました。
7回目の来院(母のみ)
前回の来院から1か月たち、最近の様子・薬の副作用について医師と話し合いました。
食欲が減った件に関しては、あまり食欲がわかないようだが、以前の量は食べられるようになったので様子観察。
寝つきが悪い件に関しては、あまりにひどくなる場合は入眠剤を検討することもあるようですが、夜の9時から9時半くらいには眠れているのでこちらも様子観察。
現段階では入眠剤の使用はしないという方針になりました。
通院頻度はどのくらいか
8回目からは特に変わりがなければ母のみ来院し、薬の処方箋をもらう。
コンサータ錠は、第一種向精神薬に分類されるお薬で30日分までしか処方できません。
1か月に1度処方箋をもらいに母のみ来院し息子の様子(症状の変化や副作用について)を伝えます。
約3か月毎(小学校の長期休暇に合わせて)に息子も来院するスタイルで通っています。
発達障害のよりよい治療のために
適切な治療を行っていくためには、家庭と学校と医療機関が連携を取る必要があります。
息子の場合、勉強中でも何か気になるものがあるとすぐに集中がきれてしまいます。
そのため、学校の先生に「座席は窓側や廊下側を避け、できるだけ1列目か2列目にしてほしい」と伝えました。
担任の先生も、息子が授業中ボーっとする様子がみられることや不注意で忘れ物が多いことを理解していたため、座席の配慮や忘れ物をしないよう声かけしてくれたりと配慮してくれました。
1年生から2年生に進級するクラス分けでは、仲が良すぎるお友達とはできるだけ別のクラスにしてほしい点をお願いしました。
理由としては、仲が良すぎるあまり会話に夢中になってしまい、先生の話を聞かない(聞こえていない)可能性があるためです。
学校の先生に「配慮」をお願いする際の伝え方
お願いする方法としては、要求ばかりを伝えるのではなく、
「いつもお世話になっています。〇〇な症状があり、病院の先生から〇〇すると良いと教えていただきました。配慮していただけると、子どもも集中できるし、先生にもご迷惑をおかけすることが少なくなるかもしれません。」と伝えます。
先生に対する感謝の気持ちと、専門の医師がおすすめしていた方法(私のわがままな要求ではないことを伝える意味も含めて)を実施してほしいこと、配慮してもらうことで先生にもメリットがあることを伝えました。
また進級する際には、どんなクラス分けになるのか・担任の先生はどんな人なのかわかりません。
しかし、年度末の面談の際に「進級するにあたって配慮してほしいことを伝え、次の担任になる方に情報を引き継いでもらいたい」旨を、伝えておく方がスムーズです。
モンスターペアレントと思われないか心配な気持ちもありましたが、根拠や理由を説明すると先生も納得してくれました。
まとめ
発達障害かどうか悩みながらも、診断をつけたくない。
また、診断がついても学校の先生には知られたくないと思うご両親がいるかもしれません。
しかし、学校の先生に症状を伝えることで、学校側が児童に必要な環境づくりなどを配慮してくれることもあります。
環境調整を行うことで、授業を集中して受けることができるなど学習意欲にもつながります。
少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
息子が発達障害と診断される①~初診内容・検査方法・診断結果とは~
0歳の時から感じていた「発達障害ではないか」という不安。
年齢が上がるにつれて、たぶんわが子はADHD(注意欠如・多動性障害)だろうと思い悩む日々。
ついに小学生になり、発達クリニックを受診する日がきました。
今回の記事では、初診の内容や発達障害の検査方法、診断結果について紹介したいと思います。
クリニックによって検査方法は異なる可能性があります。
長男が通うクリニックでの内容になりますが、参考にしていただければと思います。
初診の内容とは
初診予約をしてから三か月後。ついに初診日がやってきました。
まず看護師と母で面談。(初診日より前にクリニックの看護師とオンラインでヒアリングを行っていたため、その内容の確認)
看護師の面談後、医師の診察となりました。
医師の診察では、息子に「学校での生活は楽しですか?」、「なんの教科が好きですか?」
「お休みの日は何をして遊びますか?」など、穏やかな口調で質問していました。母はドキドキしながらも見守るのみ。
息子は椅子に座って返答していたが、医師の優しい雰囲気を察知したのか、途中から椅子を立ち診察室内をウロウロ。
その後もずっと、ウロウロ歩き回りながら質問に答えていました。
一通り息子との会話が終わったので、息子は別室へ。
次に医師と母のみで診察。
看護師とのヒアリング内容を参考に、今までの経過と現段階で困っている下記の症状を伝えました。
- 出産後から感じている育てにくさ
- 集中力が持続しないこと
- 忘れ物が多いこと
- 衝動的に行動してしまうことがあること
- 話を聞いても返答が的を得ないこと
- ADHDではないかと思っていること
今後の予定は、まず2日に分けて発達障害に関する検査を行い、後日その結果を報告する。
結果をもとに、どのような治療方法を行っていくかを検討するということでした。
本日はこれにて診察終了となる。
検査内容とは

2回目の来院
本日は検査のみ。検査は息子と心理士の2人のみで実施。
2時間くらいの検査になるため、母はその間にADHD評価スケールなど検査用紙を記入し、息子の検査が終わるのをまつのみ。
ADHD評価スケールは注意を集中し続けるのが難しいなどの不注意に関する9項目、授業中に席を離れてしまうことや質問が終わらないうちに答えてしまうことがあるなどの多動性や衝動性に関する9項目の計18項目について、0点(ない、もしくはほとんどない)から3点(非常にしばしばみられる)の4段階で評価します。
ADHD評価スケールは、事前に小学校の担任の先生に1枚記入してもらいクリニックへ持参しました。
3回目の来院(患者の状況に応じて検査を1日で実施する場合もあるそう)
本日は約1時間位の検査のみ。母は検査が終わるのをまつのみ。
4回目の来院(母のみ)
心理士から、検査の内容と結果報告を受けました。
実施した検査は【WISC‐Ⅳ知能検査】と【行動観察】でした。
【WISC‐Ⅳ知能検査】
| FSIQ全検査 | 全体的な水準 |
| VCI言語理解 | 言葉で理解する力、言語の知識や説明力、社会的なルールや一般常識の理解度 |
| PRI知覚推理 | 目で見て理解する力、複数の資格情報をまとめてとらえる力 |
| WMIワーキングメモリ | 耳から聞いて記憶する力、短期的な記憶の保持、操作 |
| PSI処理速度 | 単純作業の正確性とスピード、素早く情報を処理する力 |
【WISC‐Ⅳ知能検査】では、それぞれの項目を点数化し、平均と比べての差・項目ごとの差などがわかります。
また、全体的な知能水準、項目ごとの得意なこと・苦手なこと、検査時の様子や本人にあった対応方法やサポート方法を詳しく説明してくれました。
結果を踏まえて、今後の方針などの希望を伝えて、この日の診療は終了。
5回目の来院
まず息子と医師のみで診察。その後、医師と母のみで診察。
検査の結果を含め、「ADHD優位のASD合併」との診断を受けました。
診断後の気持ち
診断された時は、「やっぱり思った通りだった。」という納得の気持ちでした。
しかし、ASD併発とは思っていなかったので、少し困惑しました。
医師から診断についての説明を聞くと、「確かにADHDだけではなくASDの特性も持っているな」と感じました。
今までずっと「どうなんだろう?発達障害かもしれない?グレーゾーン?」などと何度も考えてきました。
この診断に至るまで、「正常であってほしい」という思いと「発達障害と診断してもらいたい」という複雑な気持ちでした。
誰しも、正常な子であってほしいという気持ちはあると思います。
しかし、「発達障害」と診断されることで衝動性や不注意な行動は「発達障害」による特性と認めてあげることができ、子どもも親も精神的負担が減るのではないかという気持ちもありました。
今後の治療法について
今後の方針は薬の適用ありとのことだったので、お薬を始めることになりました。
次回は、ADHDの治療法・効果と副作用についてを紹介します。
小学1年生で発達障害の診断~病院を受診するきっかけと初診待ち事情~
これまでに、発達障害の特徴と0・1歳、2歳、3~5歳の長男の体験例を紹介してきました。
今回は、小学校に入学した長男が発達診断と診断されるまでの経緯と実際に初診を受けられる医療機関の探し方について紹介したいと思います。
発達障害とは
発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの特性で、いくつかのタイプに分類されています。
また、1つの障害だけでなく2つ・3つと合併して症状をもつことも多いです。
自閉症スペクトラム障害(ASD)
相互的な対人関係の障害、コミュニケーションの障害、行動の偏り(こだわり)の3つが主な特徴です。
注意欠損・多動性障害(ADHD)
多動・衝動性・不注意が主な症状です。その中でも、多動・衝動性優位型、不注意優位型、混合型に分類される。
多動・衝動性の症状には、小学生では座っていても手足を動かす、席を離れて歩き回る、じっとしていられない、順番を待つのが難しい、先生が話している途中に発言するなどがあります。
不注意の症状には、学校の勉強でうっかりミスが多い、課題に集中し続けることが難しい、話しかけても聞いていないように見える、気が散りやすい、忘れ物が多いなどがあります。
多動症状は、一般的には成長とともに軽くなる場合が多いですが、不注意や衝動性は成人まで続くこともあります。
学習障害(LD)
全般的な知的発達には問題ないが、読む・書く・計算するなど特定の事柄のみ困難を要する症状です。文字の読み書きができるようになってからなので、小学校2~4年生頃に成績不振などから明らかになることが多い。
発達障害と診断される経緯
発達障害と診断される施設を受診する経緯としては、次の3パターンになります。
- 健診で指摘され、初診をすすめられるケース
- 保育園・幼稚園・小学校の先生から初診を進められるケース
- 健診や小学校等で指摘はされていないが、発達障害ではないかと思い初診を受けるケース
長男の場合、健診や幼稚園・小学校から発達に関して指摘されたことはありません。
幼児期は、定期的に幼児相談に通いましたが、現段階では「発達障害」と診断することは難しいと言われました。
理由としては、
・知的遅れがないため
・ADHDの症状なのか・年齢による行動の範囲内なのか幼児期で判断することが難しい
長男は落ち着きがなく衝動的な行動をすることがありましたが、幼児期では発達障害でない子もふざけて走りまわる子や、落ち着きがない子もいるとのことでした。
小学校に入学後も発達障害か気になるようなら、受診してくださいと言われていました。
長男が小学校へ入学した後の様子とは

幼児期に相談した際、「小学校入学後まず2,3か月様子を観察してください。夏休み前に個人面談があるので、担任の先生に授業中の様子など気になる症状がないか聞いてみてください。」と言われていました。
長男は小学校入学後、毎日楽しく学校へ通っていました。
授業中に立ち歩くことや、授業を妨害したりなどはない様子。
学校生活で気になることは、とにかく忘れ物が多い。毎日水筒を忘れて帰る。
(1年生はよく忘れ物をしてしまうこともありますが、長男はほぼ毎日)
翌日、「昨日の水筒も忘れず持って帰ってね。」と伝えるものの、それでも忘れることもあります。
忘れ物をすることがほぼ日常化しているため、何度言ってもなおりません。
授業中での様子は、きちんと椅子に座っているが時折ボーっとしている様子がある。
集中力が持続せず、聞いているのか聞いていないのかわからない時があるとのことでした。
発達クリニックの初診を決意するきっかけとは
学校の個人面談では、忘れ物や集中力などが気になるが特に何か問題になるような行動はないとのことでした。
しかし、相変わらず家では落ち着きがなく、弟に対しては衝動的にものを取ったり叩いたりと喧嘩が絶えない日々。
「発達障害」という言葉が頭の中でよぎりながらも様子観察していた小学1年の6月、学校の眼科健診にひっかかり眼科を受診することになりました。
思いのほか視力が悪く、眼鏡を作成しなければならなくなったのですが、この眼科受診が大変でした。
視力検査をしようを思えば、引き出しにしまってあるレンズが気になり触ろうとする。
「触らないでね。」と注意されるも、お構いなしに触ろうとするため時間がかかる。
<C>の向きを聞いても、時間がたつにつれ、だんだん「上?こっち?んー、やっぱりこっち?」とあいまいな返答。
結局その日はうまく視力検査ができず、後日正確な視力を検査することに。
後日、調整を休ませる目薬を点眼して再度検査をすることになりました。
この日の視力検査はスムーズに終わったものの、診察中も機械を触ろうとしたり椅子をクルクル回し遊ぼうとしたりと落ち着かない様子。
ここで眼科の先生が一言。
「何か発達的な問題あったりしますか?」
私はすかさず「今まで指摘されたことはないですが、私もそうではないかと気になっていて。」
眼科の先生は、「私は専門ではないので診断はできませんが、一度受診してみてもいいかもしれませんね。」と言われました。
この眼科受診をきっかけに、発達障害を診断できる病院の受診を決意しました。
発達障害の診断が受けられる場所は?
発達障害と診断されるには、発達障害の診断ができる小児精神科・小児神経科・発達専門外来の施設を受診しなければなりません。
自治体で相談する場合は、基本的に住んでいる市区町村にある施設の紹介になります。
インターネット検索では、市区町村は違うが比較的家から近いクリニックがある場合に便利です。
また、クリニックのホームページを見ることで初診からの流れや施設情報を詳しく知ることができるので、自治体や小児科への相談と併用して活用してみるといいかもしれません。
行政の医療機関のメリット・デメリット
<メリット>
- 自治体に相談した場合に紹介されるため、自分でクリニックを探す手間が省ける
- 行政機関のため学校との連携がとりやすい
<デメリット>
- 医師が定期的に変わる可能性が高い
- 診療は平日9時~17時まで、土日祝は休みのため診察の際は学校を休む必要がでてくる
民間クリニックのメリット・デメリット
<メリット>
- 担当医師が変わらない安心感がある
- 夕方や土曜日も診療しているクリニックも多い
<デメリット>
- クリニックによっては、予約料などを設定している場合がある
- クリニックによっては、夕方・土曜日に診療していても予約が混雑し、なかなか希望する日程の予約がとれないこともある
- 学校との連携は基本的に親が行う必要がある
私が実際に相談した場所とは
私は、まず自治体で紹介される施設に相談しましたが、初診6か月待ちとのことでした。
初診予約をしたうえで、ほかに診断できるクリニックがないかインターネットで検索し、かかりつけの小児科にも相談しました。
小児科では、自治体で紹介される施設と比較的近い距離にある発達障害専門クリニックを教えてくれました。
小児科で教えてもらった発達クリニックは、初診予約3か月待ち。
こちらも初診予約をし、初診日が来るのを待ちました。
まとめ
発達クリニックを受診すると決意したものの、実際初診が回ってくるのは早くて3か月後ということでした。
自治体によって初診待ちの長さは違うと思います。
しかし、発達障害が認知されてきて受診したい人は増えているものの、小児の発達障害を診断できる施設は少ない。
そのため、どこの施設も初診を受けるまでに時間がかかるそうです。
少しでも気になる場合は、まず自治体に相談し病院を受診するかどうか早めに検討することをおすすめします。
わが子は発達障害?自治体に相談したら紹介された「親子教室」の内容とは
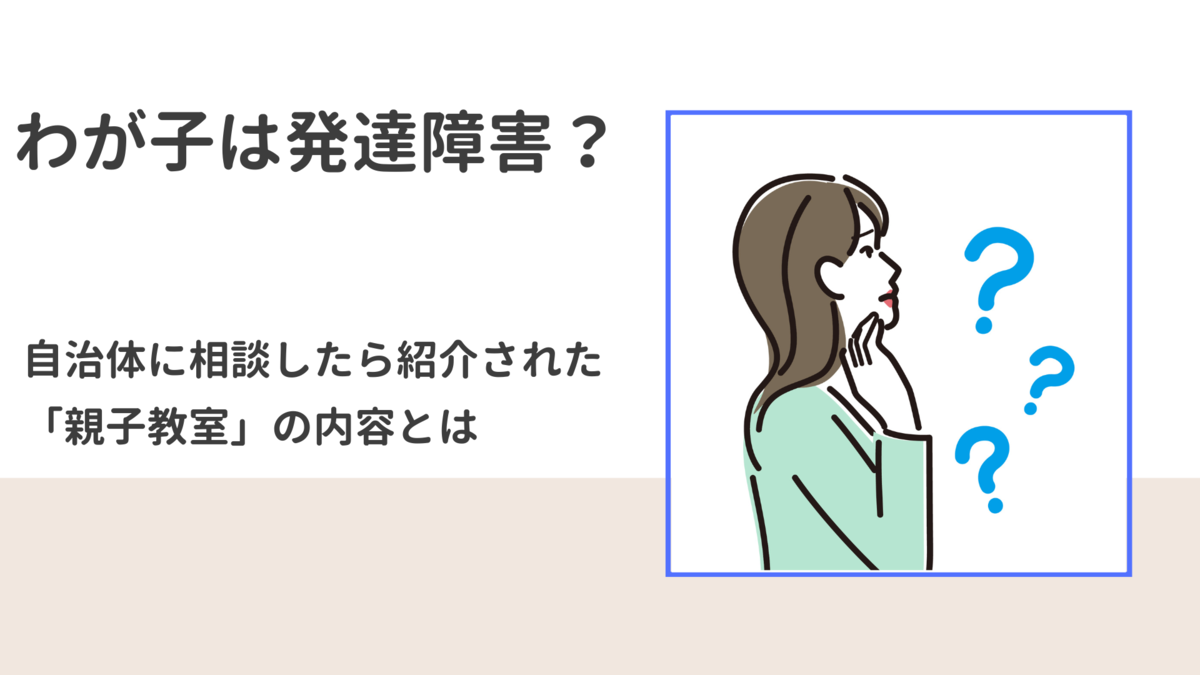
前回2歳児のわが子の様子とともに、行政に相談した結果「親子教室」に参加したという話をしました。
参考までに、発達障害の特徴と実際の体験例(2歳編)はこちら。
今回は実際に参加した「親子教室」の内容を紹介したいと思います。
各自治体で内容が異なる場合もありますので、参考にしていただければと思います。
親子教室とは
私が参加したのは、2017年の内容になります。
(内容は変わる可能性がありますので、お住いの自治体へ要確認。)
- 対象者:2歳児(2~3歳)
- 開催時間:1週間に1回、1時間半くらい
- 期間:約1か月~1か月半ほど
- 開催時期:不定期(年4回ほど実施)
- 場所:住民表のある地区保健センター
親子教室に参加するには
市のホームページ上では「親子教室」について掲載はしていないとのことでした。
基本的には、1歳半健診で発達に気になることがあった子どもに対して、案内することが多いそうです。
また、自治体に発達や言葉の遅れなどについて相談に来た方に案内することもあるとのことでした。
親子教室の内容とは
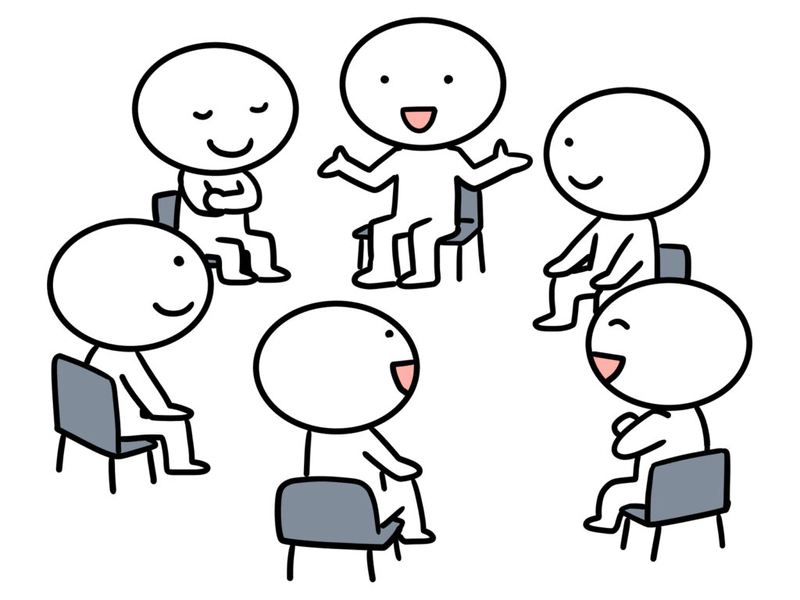
親子教室の間は、次男をボランティアスタッフの方が預かってくれたので、下のお子さんがいても参加できる体制になっていました。
参加している親子は計10組くらいでした。(子ども1人と親1人で参加)
私が参加した時の参加者は、約7割の方は発語が遅いことが気になり参加されている方、約2~3割は落ち着きがないことが気になり参加されている方という形でした。
- 前半は子どもと触れ合い一緒に体を動かします
- 後半は、親と子で少し距離をとり部屋の前後に分かれます
- 子ども達はスタッフの方が一緒に遊んでくれます
- 親は臨床心理士の方を中心に円になり、それぞれ困っていることなどを相談します
同じような悩みで参加されている方が多いので、誰かが質問した内容に対して我が家ではこう対処している、など周りの意見を聞けたり、心理士の方が対処法を教えてくれたりととても有意義な教室でした。
まとめ
次男が産まれてからというもの、次男に手をかける時間が多く長男と2人きりで過ごす時間はほとんどありませんでした。
親子教室の間、2人で遊ぶ時間は長男も楽しそうな様子でした。
親子教室では、悩み相談に対しての対処法を教えてもらえ、悩みをみんなで共有することで自分の不安を軽減できたと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
わが子は発達障害かも?と思って 自治体に相談してみた結果
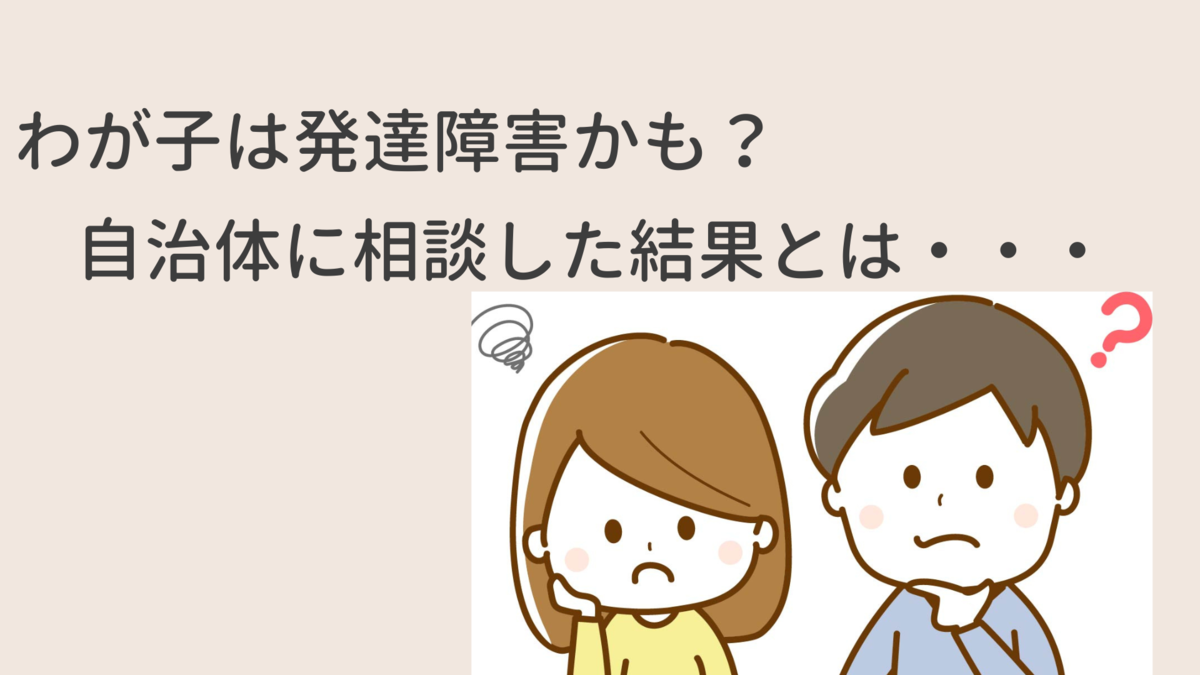
近年『発達障害』と言う言葉を耳にすることが多くなりました。
私もわが子が発達障害かもと思いインターネットを検索した結果、大部分のサイトに「気になる場合は自治体へ相談してみてください」と言う言葉を見かけました。
自治体に相談した場合、「その後どう対応されるのだろう?」、「相談したら病院を紹介され発達障害と診断されてしまうのではないか」と思い、相談することを迷っている方がいるのではないでしょうか。
今回は実際に自治体へ相談した場合、その後どういう対応になるのかを紹介していきたいと思います。
お住いの自治体によって少し内容は異なるかもしれませんが、参考にしていただければと思います。
自治体の窓口に相談をした後の対応とは
まず最初に住んでいる自治体に電話もしくは直接役所に行き相談する(待ち時間や移動時間がない電話がおすすめです)
その際に子供の発達について、子育てで困っていることなどを担当保健師に相談。
その後、保健師による家庭訪問など自宅での子どもの様子を確認し、幼児相談を受けることになりました。
幼児相談の内容とは
幼児相談は乳幼児から小学校入学前までのお子さんが対象。
- 自治体の保健福祉センターの部屋で実施(約1時間程度)
- 最初に臨床心理士の方が子どもの知的検査を実施する
(質問に対して返答する検査、積み木による検査、カードによる検査、絵をかいたりする検査、発語についての検査などの検査を一通り実施、実年齢との知的遅れがないかの評価をする) - 検査後、子どもはスタッフの方がおもちゃを持ってきてくれ少し離れた場所で遊ぶ
- その間に、親と心理士の方で話しをする
現在の家での過ごし方、友達や兄弟との関係性、何か困っていることなどを相談することができる - 相談したことに対して、心理士さんが本人の特性を踏まえたうえで、どのように親が対応していけばいいかを教えてくれる
いつも1~5の順で、相談し時間になったら終了するという流れでした。
長男の幼児相談の体験例
幼稚園入園の前の年の夏に親子教室を受け、冬頃に幼児相談の1回目を受けました。
幼児相談の終わりに、次回予約をとり終了。
長男の場合は幼稚園入園後の5月ごろにまた入園後の様子を聞かせてほしいとのことで、約半年後くらいに2回目の幼児相談を受けました。
幼稚園入園後、入園しての本人の様子はどうか、幼稚園で何かトラブルなどはないか、親が何か困っていることはないかなどを相談。
親が特に相談する必要がなくなったと思えば、幼児相談は終了になりますし、定期的に相談にのってほしい、子どもの様子を長期的にみてほしい希望があれば継続して相談することができました。
長男の場合は、幼稚園入園前、年少児の5月、年少児の秋頃、年中児の春頃、年中児の秋頃と計5回幼児相談に通ったと思います。
担当の臨床心理士の方は継続してみてくれるので話はスムーズに進みました。
長男が通ったのは4年ほど前になるので、2022年5月現在の状況を区役所に確認したところ、1回で終了する場合、1回目の相談から半年ほど経過した時期に2回目の幼児相談の予約をする場合など、相談内容や子どもの状況に応じて回数は異なるとのことでした。
また、幼児相談を3~4回ほど実施した段階で「幼稚園や保育園などの集団生活で様子をみて過ごす」もしくは「リハビリセンターなどの療育機関を紹介する」等のご提案させていただくなどの方向性を決めていくそうです。
幼児相談に通って良かったこと
臨床心理士の方に知的検査をしてもらう中で、子ともの特性や苦手な部分を知ることができました。
長男の場合は、視覚優位で聴覚からの情報は伝わりにくいとのこと。
この場合、口頭で伝えるだけでなく、できるだけ実物を目で見せて伝える方が理解しやすくなるそうです。
例えば幼稚園で制作をする際、「お道具箱から、はさみ、のり、クレヨンを持ってきてください。」と口頭で伝えるだけでは、お道具箱に物を取りに行ったものの何を取り出すのかを忘れてしまうことも多いのです。
そのため「担任の先生に、子どもに口頭指示する際は、可能な場合は実物を見せながら指示するようにお願いしてみるといいですよ。」と対応方法を教えてもらいました。
また、幼稚園に行くまでの準備がなかなか進まず、何度も注意することがありました。この場合も口頭で指示してもなかなか伝わらないため、ホワイトボードにマグネットを貼ってリスト化し、終わったら裏返すなどの工夫をすることにしました。

実際に使用していたホワイトボードです。
字や絵が下手で申し訳ないのですが、参考までに。
3歳の時にひらがなが全く読めないため、シールや絵を書いてみたり、表と裏の色を変えたりしました。
終わったものは裏返すことで、次は何をすればいいかがわかりやすくなります。
毎日思うように行動してくれない長男にイライラしていましたが、少しの工夫で改善することもあり、子どもの特性をきちんと理解することは大切だと実感しました。
まとめ
行政での相談は、保健師や臨床心理士の方の視点から子どもをみてもらうことで、親が気づいていない特性を教えてもらうことができました。
また、苦手な部分やその対応方法を教えてもらうことで、日常生活の負担を軽減することにもつながりました。
子どもに関して何か困っている、発達について心配など気になる点があれば、一度相談してみることをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
発達障害の特徴と体験例(3~5歳編)
こんにちは。
これまでに、発達障害の特徴と実際の体験例(0・1歳編)、発達障害の特徴と実際の体験例(2歳編)を投稿しました。
今回は、3~5歳の幼児期の特徴と小学1年生で発達障害と診断された長男が3~5歳の時の体験例を紹介したいと思います。
ぜひ参考にしてみてください。
発達障害とは
発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの特性で、いくつかのタイプに分類されています。
また、1つの障害だけでなく2つ・3つと合併して症状をもつことも多いです。
-
自閉症スペクトラム障害(ASD)
相互的な対人関係の障害、コミュニケーションの障害、行動の偏り(こだわり)の3つが主な特徴
-
注意欠損・多動性障害(ADHD)
多動・衝動性・不注意が主な症状です。
その中でも、多動・衝動性優位型、不注意優位型、混合型に分類される。
-
学習障害(LD)
知的発達に問題ないが、読み書き・計算するなど特定の事柄のみ困難を要する。
発達障害の特徴【3~5歳児】
自閉症スペクトラム障害(ASD)に関する特徴
- 遊び方のこだわりが強い
- 同じもの、同じ場所、同じ順序などのルールがあり、いつもと違うと暴れだす
- 好き嫌いが激しい
- 自分の欲求をうまく伝えられず友達とトラブルになることが増える
- みんなと一緒に行動することが苦手
- ひとり遊びをして過ごすことが多い
- お友達に関して無関心である
- お友達の反応を気にせず一方的に話し続ける
- 相手の気持ちや状況を理解することが苦手(空気が読めない)
- 言葉の発達が遅い
- 言葉の発音に障害がある(ただし「サ行」、「ザ行」、「ラ行」の発音は5,6歳までかかることも多い)
自閉症スペクトラム障害は、社会的コミュニケーションにおける障害があるため、幼稚園や保育園での集団生活の中で特性が目立つようになります。
そのため、子どもが3,4歳の時期に自閉症スペクトラム障害である可能性に気付く親も多いです。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)に関する特徴
- 座っていることが苦手
- 言うことを聞かないことが多い
- 直前に伝えたこともすぐに忘れる
- 先生が話しているときに発言する
- 順番を守れない
- 運動会や発表会で周りと一緒の行動が難しい
- 先生が話していても聞いていないようにみえる
- 集中が持続しない
- お友達の行動を邪魔することがある
3~5歳にADHDの特徴が目立ってきますが、この時期に診断されることは少ないでしょう。
なぜなら、落ち着きがない・集中できないなどの程度が年齢的による通常範囲なのか発達障害によるものなのかを判断することが難しいからです。
そのため、正式にADHDの診断がくだるのは、小学校にあがった段階が多いでしょう。

発達障害である長男の体験例
自閉症スペクトラム障害に関する特徴
- インターネット、携帯などに没頭し、終わるタイミングで気持ちの切り替えがなかなかうまくできない
- 一つのことに熱中しすぎて周囲がみえなくなる
- ・3・4歳は主に一人遊びを好み、友達とのかかわりが少ない
- 特定の仲良しのお友達がいない
- 好きなことに関しての記憶力がとても良い
- 体の動かし方がぎこちなく、よく転ぶ
- ・インターネット、携帯などに没頭し、終わるタイミングで気持ちの切り替えがなかなかうまくできない
- 一つのことに熱中しすぎて周囲がみえなくなる
- ・3・4歳は主に一人遊びを好み、友達とのかかわりが少ない
- 特定の仲良しのお友達がいない
- 好きなことに関しての記憶力がとても良い
- 体の動かし方がぎこちなく、よく転ぶ
運動会のダンスがなかなか覚えられず、運動会当日もお友達が躍る姿を少しマネする程度の動きをしていました 。
- 発音がうまくできない(サ行がタ行におきかわってしまう)ため、言語リハビリに通った
私はいつも子どもと接しているため、何を話しているか聞き取れますが、実家に帰省した際に祖父母が「え?今なんて言ったの?」など聞き返すことが多くありました。
そのため、区役所に相談した結果、言語リハビリに通うことになりました。
言語リハビリの詳細については、別の記事にてまた紹介したいと思います。
注意欠陥・多動性障害に関する特徴
- お友達が遊んでいるおもちゃをいきなり壊したりする
「貸して」や「一緒にやろう」などの言葉を発する前に、衝動的な行動にでてしまうことがあり、お友達が泣いてしまうということがありました
- やりたいと思うと、周りの状況を考えず行動してしまう
- ずっと走り回るなどの多動性は少し落ち着いてきたものの、病院など特定の場所でウロウロ動きまわる
- 公文の教室で寝てしまったり、急に歌を歌いだしたり集中が続かない
- 周りの物や障害物を気にせず、よくけがをする
長男は3歳から公文の習い事を始めました。
(始めた理由と公文のメリット・デメリットはまた別の記事で紹介したいと思います)
公文では1教科約30分を目安にその日のプリントに取り組むのですが、1時間たっても2時間たっても終わらないことがよくありました。
まとめ
幼児期になると、発達障害の特徴がだんだんと目立ってきます。
少しでも気になるようであれば、一度相談してみることをおすすめします。
児童精神科や発達障害の専門外来にハードルを感じてしまったり、どこにあるのか情報がわからなかったりする場合も多いと思います。
まずは、かかりつけの小児科や自治体の発達障害窓口・家庭相談課などに相談してみるといいでしょう。
どのように自治体に相談したらいいかわからない、相談した後はどう対応してもらえるのか。
実際に私が自治体に相談した内容を、わが子は発達障害かも?と思って自治体に相談してみた結果の記事に載せていますので、参考にしてみてください。